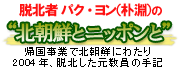

私はなぜ北朝鮮を脱出したのか(10)
周りはすでに暗くなっていた。
真っ暗な玄関の前でろうそくの明かりをつけた露店の女が、私の同僚を引き止めた。
露店に近づいた彼は躊躇することもなく酒を要求した。
もちろん、私のポケットの金を当てにしてのことであるが、いきがかり上私はその支払を避けることはできなかった。
暗い家に入ると、彼は食卓を準備するまもなく食べ物に食らいついた。
私が気を回さなければ、娘はそのまま食べそこなうところだった。
私は、娘の食べる分を分けるため、食べ物を別に管理統制する必要を感じた。
そして、そのことが、私にも何なのかはっきりわからない、抗うことのできない未知のショックを感じた。
台所では私が分け与えた食べ物を食べて安心したのか、少女は靴を履いたまま寝いってしまった。
部屋では、食べあげてしまうにしても、残しておくにしても、食べ物を離せなかった同僚が、舌をゆがめて愚痴を言い始めた。
あまりにも繰り返すので、何のことかと思うに、その内容は自分の妻についてであった。
同僚は大学生の最後に道の芸術団の俳優であった妻と結婚した。
研究者になった夫の経済水準では、女優をしていたの妻を満足させることは難しかったものの、社会的風潮が夫婦の結びつきを補った。
しかし配給制が破綻し、それにより既存の秩序に代わって新しい秩序が胎動すると、すべての美貌の女性と同じように、彼女も、離婚して解放と自由を選択する決心を夫に通告した。
抵抗もした。話し合いもした。だが、いくら頑張っても弱者の交渉は弱いものだ。
娘を引き受けることで一定の生活費は保障するという約束で、半ば譲歩し半ば承諾した。
が、契約を担保にする法制すらない北朝鮮社会では、個人間の約束に何の重みがあろう。
自由に職業と職種の選択ができるわけでもなく、麻痺した計画経済と無法がはびこる原始的市場がごちゃごちゃになってる中で、インテリが堕落していくのはよくあることだった。
私の同僚も、餓死するか、違法行為に手を染めるか、コチェビになるか、この3つの選択以外他の道はなかったのだ。
その時だった。突然、玄関が開いて懐中電灯の光が家の中を照らした。
まもなく濃厚な香水の臭いと共に、女性の鋭い声が響いた。
「子供を世話すると金はかっぱらっといて、子供は台所に追いやって仲間と酒飲みかい」
私は、我知らず跳ねる様に立ち上がった。同僚は両膝の間に首を落としたまま微動だにしない。










![<北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡 <北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡](https://www.asiapress.org/apn/wp-content/uploads/2010/12/201010070000000view.jpg)










