
![]()

![]()
東ティモールという地名には、学生時代のささやかな記憶を呼び起こされる。
75年12月、インドネシアがこの小さな島へ武力侵攻を行ったとき、私はスナックのマスターをしているアナーキストの友人Mと連れ立って、神戸のインドネシア総領事館へ抗議文を届けた。それは「運動」というようなものでもなく、たんなる思い付き程度の行動だったが、それ以降、東ティモールへの関心は途切れることがなかった。
侵略者であるインドネシアの兵士たちによって遂行された殺戮は、ジェノサイドに類同する規模と残虐さを伴っていた。私の怒りを掻き立てたのは、このような「蛮行」に対して世界が沈黙していたことである。
日本などは、インドネシアの侵略を非難する国連決議にも、一貫して反対の立場をとり、「義」や「道理」に従うよりも、利権で結ばれた独裁政権との関係を維持することにのみ腐心していた。これは唾棄すべき態度だった。欧米のおもな国々はインドネシア国軍の撤退を求める決議に賛成したのに対し、先進工業国の中で日本だけは反対票を投じていた。日本人であることをこれほど恥ずかしいと思ったことはない。
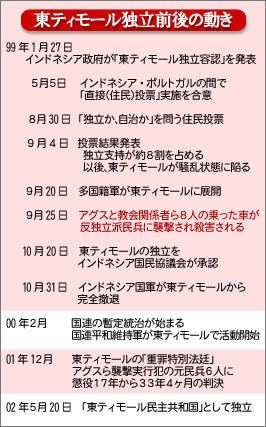 それから30年余り、戦争や紛争、難民発生の現場などで日本の「国柄」を見聞してきたが、残念ながら日本という国の国民であることを誇りに思わせてくれる機会はほとんどなかった。
それから30年余り、戦争や紛争、難民発生の現場などで日本の「国柄」を見聞してきたが、残念ながら日本という国の国民であることを誇りに思わせてくれる機会はほとんどなかった。
排他的で狭隘な「自己」しか持てない「国家」を愛せよ、といっても土台無理な話である。
東ティモールの周囲に築かれた「沈黙の壁」が自壊を始めたのは、スハルト体制の崩壊により、インドネシア内部の政治的な混乱がきわまったからである。
インドネシア国軍による侵略、占領から24年目にして初めて、独立への希望が現実のものとなろうとしていた。
その4半世紀におよぶ占領の期間、抵抗勢力の核となったのは、フレテリン(東ティモール独立革命戦線)であり、その軍事部門から発展したファリンテル(東ティモール民族解放軍)である。
東ティモールで私がいちばん行きたかった場所は、そのファリンテルのゲリラたちの活動する山岳地帯だった。わずか千数百人とはいえ、もし彼らが武装抵抗を止めていたら、その時点で世界は「東ティモールのインドネシア支配は確立された」と認識したことだろう。武力闘争は存在すること自体が、抵抗の象徴的な意味を示す。ゲリラ兵士の数の多寡は問題ではない。
アグスはガジャマダ大学に留学していた東ティモールの学生たちの人脈を使い、地下活動家たちとの接触を始めた。インドネシア人であるアグスにとっては、独立派ゲリラ取材そのものが、反国家的な行動と見なされかねない。
政府のプロパガンダを刷り込まれたインドネシア人の多くは、「東ティモールはインドネシアの一部となることで発展してきた。抵抗しているのは、ならず者にすぎない」と思い込まされていた。
しかし、アグスはまったくそのようには考えていなかったようだ。おそらく、彼の出自とも関係があるに違いない。 (続く・全7回)次(3)へ>>
【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】










![<北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡 <北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡](https://www.asiapress.org/apn/wp-content/uploads/2010/12/201010070000000view.jpg)










