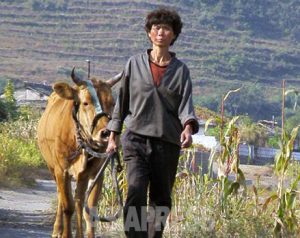◆今度こそ抜本改正を
複数のベテランの調査・分析者に見解を尋ねたところ、こう口をそろえた。
「(今回の調査ミスは)常識的にはあり得ないと思いますけど、最近は常識が通用しないとんでもない調査ミスが珍しくないので……」
石綿を見逃せば、労働者や周辺にいる人びとがばく露させ、数十年後に中皮腫(肺や心臓などの膜にできるがんで予後が非常に悪い)などの健康被害を生じさせることになりかねない。ところが調査ミスが横行しているというのだ。
ずさんな石綿調査が繰り返される原因の1つは、国の意向で現場を知らずまともな石綿調査ができない“素人”同然の「ペーパー調査者」「にわか調査者」が急増したことがある。
もともと国土交通省が2013年に始めた建築物石綿含有建材調査者(現在の特定調査者)講習は、建築などの一定の実務経験がある者を対象に、座学だけでなく実地研修も含め「中立かつ公正に専門的な調査を行うことができる調査者の育成」をめざしてきた。
ところが厚生労働省と環境省を含む3省共管に切り替わり、実地研修なしの「一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)」を新たに規定。しかし調査に制限が設けられなかったため、特定調査者講習を受講する必要性がなくなった。また「石綿作業主任者技能講習」を修了した者は実務経験なしでも調査者講習を受けることが可能になったことで受講者が大幅に増えることになった。
厚労省は実地研修を除けば講習時間は同じとして、「レベルを下げたわけではない」と強調する。しかし講習機関や講師は、「国から合格率を90%まで上げるよういわれているので、どこの講習でも修了試験の答えを教える時間を作ったり、『ここ試験に出ますよ』と教えているのが実態で、誰でも通ります」とため息をつく。同省は否定するが、関係者の間では周知の事実である。
その結果、石綿調査ができる有資格者は2024年末で約23万6700人まで増えた。そうして調査ミスが量産されているというのが現場の声だ。国の失策は明らかである。
一度講習を修了したら更新も必要ない“永久ライセンス”というのも異常である。イギリスなどでははるかに難しい認定制度のうえ、毎年更新講習を受けなくてはならない仕組みだ。調査ミスで人のいのちを奪いかねない以上、認定制度の導入に加えて、継続的な更新講習により“素人”調査者をレベルアップさせる仕組みが必須である。
さらに廃棄物処理業と同様に石綿調査・分析業者の許可(ライセンス)制度があれば、不適正な調査・分析は許可取り消しの理由になりかねず、一定の歯止めをかけることができる。イギリスのように国際標準課機構(ISO)認証による精度管理を義務づけ、品質保証する取り組みも必要だ。
イギリスでは分析機関のISO17025認証による精度管理は規則で義務づけ。調査機関のISO17020認証による精度管理を規則に基づく実施準則(ACOP)で「強く推奨」している。義務づけではないが、採用している事業者を使わない場合、不適正事案が起きた際に発注者責任を問われかねない仕組みである。この精度管理は受注現場の5%に対して別の調査者に再調査させ、結果が統計的に95%の信頼区間内であることを要求する非常に厳しいものだ。こうした取り組みにより、調査ミスが極力起きないようにしていくことが重要だろう。
いい加減な石綿調査をしてもお咎めなしというのでは、ずさんな調査はなくならないし、きちんとした調査をするインセンティブが働かない。これでは今後も被害者は出続けるだろう。今年度は前回の法令改正から5年の見直し時期だ。今度こそ抜本改正が求められる。